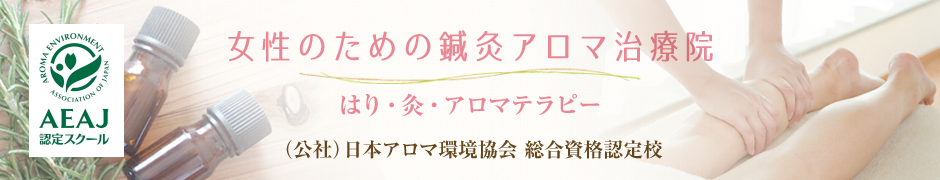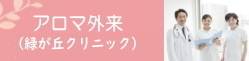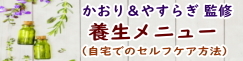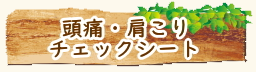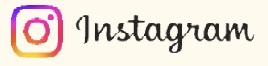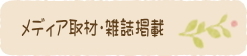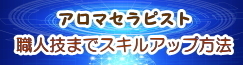風邪予防におすすめ吸入法

風邪予防のための精油吸入法
【基礎編:手洗い・うがい・精油吸入】
風邪をもらってしまったかも?と思ったら
いつもの手洗い・うがいにプラスして、
精油の香り成分を鼻から吸う
『精油吸入』がおすすめ
これは
「うがい薬で口の中をケア」と同じように
『香り薬で鼻の中をケアする』ということです。
風邪の菌やウイルスは、とても小さいので、
吸気に混じって、左右の鼻の穴だけでなく
さらに奥の小空間(副鼻腔)まで入ります。
↓下記イラストで、黄色の部分が副鼻腔

風邪や花粉症の時に、
頬や額が重く感じたことがありませんか?
または、風邪の時に鼻をかんだ後、
さらにフン!といきんでみたら
奥から鼻汁がでてきたことがありませんか?
それこそ
副鼻腔に鼻汁が溜まってしまったときの症状。
この副鼻腔という小空間は、
左右の鼻と同じ粘膜が張り廻られているので
いっちょまえに(笑)鼻水鼻汁を出します。
つまり、
左右の鼻の穴に病原微生物が付着すると、
同じ粘膜がつながっている奥の空間まで
感染が広がるということです。
副鼻腔は鼻うがいは届かないですし
奥の空間なのでケアが難しく、めんどう。
そこで、
「粒子が小さく奥まで届く
芳香成分(精油)で殺菌する」
というわけです。
精油をお部屋に香りを広げるのと違って
殺菌効果が直接期待できる行為なので、
精油の効能を確認しましょう。
(※微生物の殺菌効果が期待できる精油)
粘膜に直接ぬるわけではないので、
刺激も少なく安心して行えます。
※アレルギーや基礎疾患がある方はご注意ください。

<風邪予防の吸入方法>
◆準備するもの
・殺菌・制菌効果のある精油
・ティッシュ1枚
※手洗い・うがいを事前にすませてください。
1.精油をティッシュに1~2滴つけ、
香りがするところまで鼻に近づける
(肌にはつかないように気をつけましょう)
2.左右どちらか一方の鼻を指でふさぎます
3.開いている側(ふさいでいない側)の鼻から、
香りごと空気をゆっくり吸いこみます
4.吸い込んだ香りは、息と一緒に口から出す
5.3回繰り返したら、反対側も同様に行います
外から帰ってきたときに、手洗い・うがいとセット
で行うことをおすすめします。
※応用編の「マスクで吸入する方法」


鍼灸アロマ治療院かおり&やすらぎ